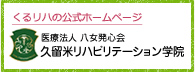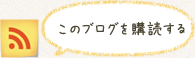病院がつくったリハビリ専門学校 久留米リハビリテーション学院オフィシャルブログ
久留米リハビリテーション学院 平成28年 実習指導者会議
2016/1/21(木)
みなさん、こんにちは。久留米リハ学院広報の仲山です。


先日、理学療法・作業療法学科の3年生が2月1日より実習でお世話になる、現場の指導者の先生方をお招きした会議が行われましたのでその様子をお伝えします。
今年は、前年より多い過去最高の131施設の指導者の方々にお越しいただきました。
まず、全体会議の中で、前年の実習についての報告及び質疑応答を行った後、各学科に分かれてさらに具体的な内容について議論いたしました。


理学療法学科 分科会 作業療法学科 分科会
最後に、実際にお世話になる学生より挨拶です。


理学療法学科3年生 作業療法学科3年生
両学科ともに意気込みを感じさせてくれる挨拶でした!
今回の実習を経て、4年生では長期実習が控えております。
それぞれの実習で大きく成長してくれることを期待しています!
3年生のみなさん、しっかり頑張ってきて下さい!応援しています!


先日、理学療法・作業療法学科の3年生が2月1日より実習でお世話になる、現場の指導者の先生方をお招きした会議が行われましたのでその様子をお伝えします。
今年は、前年より多い過去最高の131施設の指導者の方々にお越しいただきました。
まず、全体会議の中で、前年の実習についての報告及び質疑応答を行った後、各学科に分かれてさらに具体的な内容について議論いたしました。


理学療法学科 分科会 作業療法学科 分科会
最後に、実際にお世話になる学生より挨拶です。


理学療法学科3年生 作業療法学科3年生
両学科ともに意気込みを感じさせてくれる挨拶でした!
今回の実習を経て、4年生では長期実習が控えております。
それぞれの実習で大きく成長してくれることを期待しています!
3年生のみなさん、しっかり頑張ってきて下さい!応援しています!
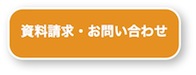 |
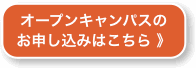 |
2016/1/21(木)
理学療法学科・作業療法学科3年生 評価実習後インタビュー
2014/3/25(火)
 みなさん、こんにちは。理学療法学科 教員の大塚 和宏です。
みなさん、こんにちは。理学療法学科 教員の大塚 和宏です。先日、評価実習の後の症例報告会の様子をお伝えしましたが、今回は学生たちの生の声をお届けします。
今回、協力してくれたのは、理学療法学科3年の井上 智恵さんと、作業療法学科3年の向井 隆晴君です。
 大塚:評価実習で、良かったことはどんなことでしたか?
大塚:評価実習で、良かったことはどんなことでしたか?向井:評価実習ではたくさんの利用者様との関わりが持てて良かったです。日が経つにつれ利用者様の方から話しかけてくださるようになって、その事がとても嬉しく実習を頑張る力にもなりました。ある利用者様から「あなたみたいな人に診てもらいたい」と言われた事がとても嬉しかったですね。
井上:毎日時間に追われていた感じですけど、患者様と接する内に、自分がPTを目指すきっかけやどんなPTになりたいか、という心を改めて振り返ることができたことが良かったです。
大塚:評価実習で意外だったことや驚いたことは?
向井:利用者様のリスク管理をしっかりされており、その情報も他部門のスタッフとも共有していて、報告、連絡、相談といった基本的なところがいかに大事であるかを改めて感じました。
井上:検査・測定では基本的な方法がありますが、臨床では結果を出すためにただ検査測定を行うのではなく、患者様の全体像を把握し、その方のキャラクターに合った工夫を凝らす必要があるということに驚きました。このような工夫は治療場面でも同じでした。
大塚:評価実習に行くに当たって、準備しておいて良かったものは何ですか?
 向井:実習では、どのような症例様になるか分からないため色々な評価を想定して評価用紙を準備しておきました。
向井:実習では、どのような症例様になるか分からないため色々な評価を想定して評価用紙を準備しておきました。井上:解剖学・運動学・生理学は、(疾患や症状の)原因追及においても考える幅を広げるために勉強しておいて良かったと感じました。
大塚:評価実習の反省を踏まえて、4年の臨床実習や、国家試験に向けての課題はどういったものがありますか?
向井:文章力や要領の悪さといった部分が実習では自分に大きな負担となり睡眠不足になってしまったんです。今後の課題としては優先順位をつけ取り組んでいきたいと思っています。また一つの事に時間をかけすぎず要領よく行っていきたいと思います。
井上:評価実習では、学校で学んだ基本的な知識や技術がそのまま反映されることはあまり無くて、臨床実習ではそれをどのように応用していくかが課題だと思っています。また、考えることを諦めず、疑問点を追求していく姿勢を身につけることも課題ですね。
 二人とも、とても充実した実習だったようですね。ご協力ありがとうございました。次は臨床実習ですね。しっかり頑張って下さい!
二人とも、とても充実した実習だったようですね。ご協力ありがとうございました。次は臨床実習ですね。しっかり頑張って下さい!評価実習が終わると、休む間もなく国家試験対策へと移っていきます。 緊張感を緩めることなく頑張っていきましょう。
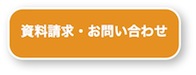 |
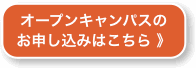 |
2014/3/25(火)