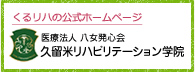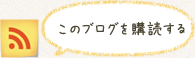病院がつくったリハビリ専門学校 久留米リハビリテーション学院オフィシャルブログ
今年ラストのオープンキャンパス開催!
2012/11/28(水)
| みなさん、こんにちは。くるリハ広報の和知です。 街の所どころではクリスマスイルミネーションが輝き、なにかワクワクさせてくれる今日この頃です。 11月24日(土)今年ラストのオープンキャンパスを開催しました。今回は鹿児島県や佐賀県からの参加がありました。また、高校2年生も多数参加され、進路に向けての意識の高さを感じました。 |
|
  |
|
| 始めに教員の紹介と今回のオープンキャンパスを手伝ってくれる学生からのご挨拶です。 | |
  |
|
| 【e-school体験】 最先端の授業!くるリハオリジナルである「e-school」からスタートです。 |
|
  |
|
| 【学院内見学】 くるリハの学生が各施設を案内して行きます。 どのような施設か、どんなことを学ぶのかなどを説明させていただきました。 |
|
  |
|
| 【休憩タイム】 参加者のみなさんも緊張がとれて、いろんな質問をされていました。 |
|
| 【作業療法体験】 今回の作業療法学科体験は前回に引き続き、今流行りのスイーツデコレーションを行いました。マグネットの上に白い土台をのせて、シリコン粘土でホイップ!自分たちの好きなパーツをのせて作品を作っていきます。 |
|
  |
|
| なぜ、このような手工芸が治療になるのか?不思議に思われる方も多くおられます。 作業療法士の言う“作業”は、生きて行く活動そのもののことを指します。私たちは、この作業を通して、手先で摘むことや、両手を協調させて動かす事や、握力を向上させる事を経験します。 また、この空間を利用して自分らしい作品を作る事が出来ます。初めて作る物は、満足する作品が出来ないかもしれませんが、次の目標が出来、失敗も成功へ導いていくことで、問題解決能力が身につき、作品への満足感や自分への有能感を得る経験、学習に繋がります。 何もないところで緊張する場面でも、作業を行いながらでは緊張がほぐれたり、会話がはずんだり、知らない人とでも仲良くなれたりします。 訓練と行うだけでは経験出来ない作業を媒介とすることで様々な経験を与える事が出来ます。そこが作業療法と理学療法の訓練の違いであると思います。 |
|
 左の写真は、参加者の方々が作った作品です。初めて作られた作品ですが、みなさんとっても綺麗に作ることができましたね! 左の写真は、参加者の方々が作った作品です。初めて作られた作品ですが、みなさんとっても綺麗に作ることができましたね!本日のオープンキャンパスの記念にお持ちかえりいただきました。 |
|
| 作業療法学科教員 服部 綾子 | |
| 【理学療法体験】 | |
  |
|
| 今回の理学療法体験では、「バイタルサイン」について説明させていただきました。 病院などで患者様の状態を把握するためには、「バイタルサイン」を適切にチェックすることは非常に大切です。 本日は「血圧測定」を中心に実技を行いました。理学療法を行ううえで、ベッド上にいらっしゃる患者様が今どの様な状態にあるのかを知り、どの様な形で訓練を行うかを考えなければいけません。 |
|
 理学療法士・作業療法士はその患者様との訓練の中でリスク管理が大切です。 理学療法士・作業療法士はその患者様との訓練の中でリスク管理が大切です。今日のオープンキャンパスの体験は、その一部です。 参加された皆さんいかがでしたでしょうか! まだまだ話したい内容がいっぱいありましたが、時間の都合上ここまでで終わりました。もっと詳しく聞きたいと思われた方は是非、本学院に入学して学んで下さい。 |
|
| 理学療法学科教員 金川 潤也 | |
 最後に今回から企画しました「サークル紹介&本日のオープンキャンパスのダイジェスト」をご覧になっていただきました。 最後に今回から企画しました「サークル紹介&本日のオープンキャンパスのダイジェスト」をご覧になっていただきました。このダイジェストはこちらからご覧になれます! |
|
| 携帯サイトはこちら | |
| 【オープンキャンパスに参加者した保護者様の声】 | |
|
|
| 今年度のオープンキャンパスも残すところ後1回(平成25年1月12日)となりました。 この日程で参加出来ない方には、随時学院見学を開催しています。平日はもちろん土曜、日曜、祝日も対応したします。お気軽にお問い合わせ下さい。(フリーダイヤル0120-707-177事務部) また、受験を検討している方がおられましたら、早めの受験をお薦め致します。定員数が充足した際には残り試験を中止する可能性があります。 |
|
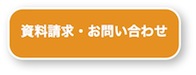 |
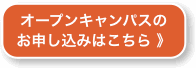 |
2012/11/28(水)
防災総合訓練実施
2012/11/20(火)
みなさん、こんにちは。くるリハ広報の和知です。
今年も残すところ約1カ月半となりました。
暖房器具や、冬物の洋服などの準備は終わりましたでしょうか!冬の気配が日に日に感じられるようになったこの頃です。これからの季節は空気が乾燥し、火災が発生しやすくなります。
さて、本学院では11月14日に防災総合訓練を実施しました。
 ・出火場所は2階基礎医学 教室!
・出火場所は2階基礎医学 教室!
・非常ベル作動後に非常電話を使って
全館放送!
・学生全員、中庭に避難!
・教員は学生の避難誘導及び、消化器と消火栓
ホースを持って消火活動!


消火活動が終了し、学生と教職員が全員避難したところで、八女消防本部の方から指導及び、講評をしていただきました。学生も緊張感を持って速やかに避難したことなど、高い評価をもらうことができました。今年に入ってこの地区では火災で2名のお年寄りの方が亡くなったそうです。
今回は学生全員が高い意識を持って真剣に取り組めたと思います。これから就職する病院や施設、家庭などで、本当の災害の際はどのような場面でどのように起こるかわかりません。今日の訓練を活かし、慌てず、冷静に患者さんやご家族を避難させることができるように努めていただきたいと思います。
2012/11/20(火)